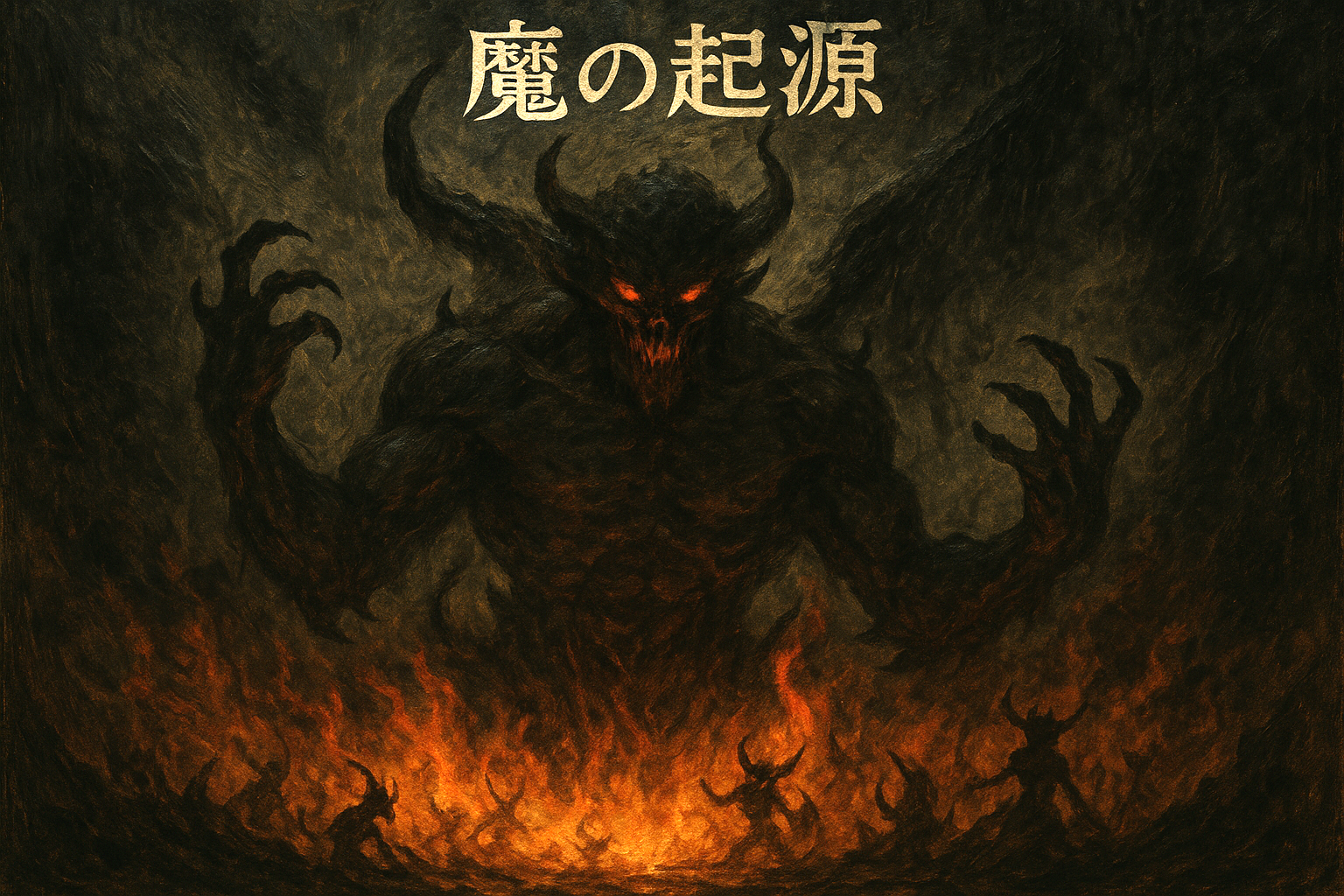「魔の起源」という本に載っていた山の神の解釈が後味悪かった。
503 :名無しさん@おーぷん :2016/02/23(火)23:59:02 ID:HDt
山の神は、名前のとおり山に住んでいるといわれる人の姿をした神で、目と足が一つづつしかない。
本の中で、山の神に関するこんなエピソードが古典から引用されている。
山の神が村に下りてきて人を襲った。
襲われた人は「あわあわ」などと悲鳴を上げながら、抵抗らしい抵抗もできず山の神に殺された。
山の神は鬼なのだ。
山の神が村に来た理由も人襲った理由も、村人たちが黙って山の神が暴れるのを見ていた理由もなく、「鬼なのだ」としか記されていない。
著者はこのエピソードに対し、以下のような考察を述べている。
かつては日照りなどの際に、神に人間のいけにえをささげる風習があった。
そして身寄りのない人間や流れ者などを、いけにえ要員として『飼って』おくことがあった。
いけにえ要員に逃げられては困るので、逃げられないように片目をつぶし片足を奪ったという。
それが片目片足の『山の神』の正体だ。
殺されるために生きている身が哀れだったので、時に暴れまわっても村人はとがめたりしなかったのだろう。
当時は、日照りや冷夏などの異常気象が、即、村単位の死活問題になるハードモードだったから、現代人の感覚で物を言ってはいけないのは分かるけれど「いけにえ要員の飼育」という考え方はやりきれないものがあった。
(了)
追記:二〇二五年十一月十三日
本資料に引用された「山の神」の解釈は、柳田國男『一目小僧その他』(昭和十七年刊)に収録された考察と一致する。柳田は、山の神が片目・片足という不完全な姿で語られる点に着目し、その異形性を古代における生贄儀礼に由来するものと論じた。すなわち、日照りや冷害などによる飢饉が直ちに村落の存亡にかかわる時代において、人々はその危機を回避するために神に人身を捧げる風習を持っていたとされる。
その際、生贄は単なる外部からの捕縛者ではなく、村落内部で「神に属するもの」として一定期間「飼養」される存在であった可能性が指摘される。ところが、生贄が逃亡すれば祭祀の秩序は破綻するため、逃走防止の処置として片目を潰し、あるいは片足を奪うといった身体的欠損が施されたと推測される。このような処置を受けた人々の記憶が、伝承において「片目片足の山の神」として投影された、というのが柳田の見解である。
本解釈は、山の神の異形が単なる想像的怪異ではなく、社会的儀礼に基づく歴史的現実の反映であることを示唆している。すなわち、神の姿は人間の行為の記憶を象徴化したものであり、同時にそこには共同体の罪責が刻印されていると考えられる。伝承における「山の神の暴走」や「村人が咎めなかった」という描写も、実際には生贄として拘束された人々の抵抗や絶望の表象であり、それを正面から否認できなかった共同体の心理的態度を示すものと解釈し得る。
ただし、この説はあくまで民俗学的推測の域を出るものではなく、具体的な史料による裏付けが存在するわけではない。それにもかかわらず、異形神の姿を「社会が生み出した犠牲の痕跡」として位置づける試みは、民間伝承を単なる空想物語ではなく、過去の社会構造や人間行為の記録として捉える視点を提供する。したがって「山の神=不具の生贄説」は、伝承研究における象徴解釈の一つの重要な事例と位置づけられるだろう。