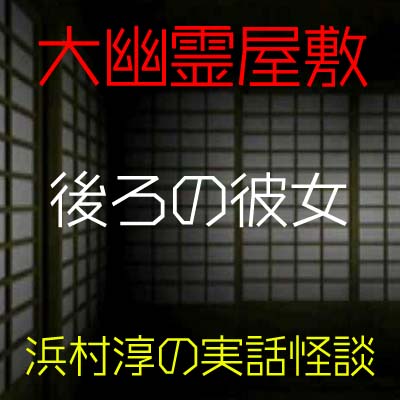第30話:後ろの彼女
兵庫県神戸市にある、六甲山ハイウェイという険しい道路はバイク乗り達の間では、”天国と地獄”と言われている。
何故、”天国と地獄”と呼ばれているのかというと、このハイウェイのカーブがとても激しいために、行動をレース場に見立ててタイムを競う「走り屋」にとっては、実に走りがいのある、うってつけのレースコースとなるからだ。
カーブと一口に言っても、実にたくさんのバリエーションがある。極端なカーブ、長いカーブ、坂道から傾斜のかかったカーブ等、様々なカーブがある。
だから、走ることを楽しみとする走り屋たちにとっては天国のようなハイウェイなのである。
しかしその反面、”地獄”と呼ぶにふさわしい程、死亡事故も多い。
六甲山ハイウェイには、普通に運転するだけでも急過ぎると感じるカーブがたくさんある。
どんなに運転に自信のある人でも、少し気をゆるめれば谷底に転落死してもおかしくないほど危ないコースなのだ……
さて、今日は貴方に、そんな六甲山ハイウェイで恐怖体験をしてもらいたい。
しかし、その前に一つ忠告しておきたいことがある。
以後、六甲山ハイウェイへ出かける機会があったときには、どうか十分に注意してもらいたい。
なぜなら、これからお話する話の体験者である私の先輩は、このハイウェイで死んでいるからだ……
もしかしたら、その先輩が貴方を事故に巻き込んでしまうかもしれない……
走り屋が集まる所、イコール若者だ。ここはデートスポットでもある。夏には若いカップルたちで賑わう。
先輩もそんなカップルの一組だった。
先輩は丁度夜景がきれいな時間帯を選んでバイクの後ろに彼女を乗せ、暗い六甲山を爆音をたてながら突っ走っていた。
先輩が彼女を後ろに乗せるのは初めて。
自分のバイクの腕を彼女に見せたい事もあって、少々飛ばし過ぎているようだ。
それに、フルフェイスのヘルメットを深く被った先輩には、ノーヘルの彼女の悲鳴も聞こえない。
「K!!スピード出しすぎ!!恐いわ!落としてぇ!!」
そんな彼女の闇夜を引き裂くような悲鳴も、先輩には風の口笛ぐらいにしか聞こえなかった。
先輩は今日、彼女といい仲になりたかったので、ちょっと裏道を走っている。
走り屋たち、そしてナンパ男たち以外はあまり使わない裏道だ。
今走っている所から2キロ程下がっていった所に、見通しのいい展望台がある。
2キロと言っても曲がりくねった山道のことである。直線にしたらいくらもないだろう。
現に、木立の切れ間から下をのぞくといくらか明かりの集まっているのが目にはいる。
あそこが展望台だ。
先輩は神戸の美しい夜景をみながら、愛を語ろうという魂胆だったのだ。
先輩は展望台についた後でんな話をしようか、などと考えながら、長い下り坂を疾走する。
各々のカーブの手前、そして終わりに配置された交通標識に混じって、”いのしし注意”などの看板なども見られる。
六甲山は、自然と動物の宝庫でもあるのだ。
先輩が走っている所も、そんな看板やツタが生い茂った、うっそうとした所だった。
時折、バイクのライトが森の中を照らすと、ギラギラと不気味輝く沢山の目がある。
動物達の目か、それともここで事故死した者たちの亡霊か……
先輩もそのとき薄気味悪さは感じていたという。
だから、早く展望台へ着こうという気持ちが強くなり、アクセルを大きく回していったのだろう。
一つ、二つ、先輩のバイクはカーブをクリアしていく。
カーブをクリアする毎に、彼女の両手は先輩の体に深く、深くしがみついていくのだった……
しかし、厳しい下り坂カーブを曲がりきった直後、彼らの目の前に事故で壊れて道に突き出た、鋭利な交通標識が行く手を遮ったのだ。
車がぶつかっていったのであろう、標識の柄であった部分は原型をとどめていない。
が、その切っ先はまるで剃刀のような鋭い光で、先輩たちを待ち受けていた。
かなりスピードがでた状態でカーブを曲がり、しかも目の前に急に障害物が出てきたとあっては、さすがの先輩も進路変更は無理だ。
必死の思いで、首のあたりまでせまったそのシャープな剃刀のような標識を、右に体を倒してフッと避けるしかなかった。
ヘルメットの中、額に油汗がにじんでいるのがわかった。
心臓の鼓動がきこえる。
風の音が異様に大きく、耳に入ってくる気がした。
バイクのバランスを立て直し、次なる下り坂カーブへ突入。
危機一髪で事故を免れたと、ホッと胸をなで下ろしていた先輩だった。
展望台までもうすぐだな。そう思える余裕さえあった。
そして、そこではじめて、このバイクに乗っていたのは自分一人ではない事を思い出したのだ……
さっきから、腰にまわされた彼女の手がやけに強く彼の腰を締め付ける。
まるで、太いロープで胴体を縛りつけられているような感触がする。
「おい!!大丈夫か?!」
返事はない。
スピードを落とし、後ろの彼女に声をかけるセンパイ。
風の音が止んだ。
いままで耳元でうるさいくらいにうなりを上げていた風の音が。
辺りには先輩のバイクのマフラーの音だけが、こだましている。
「おい!!大丈夫か?!!」
先輩はもう一度きく。
やはり彼女からの返事がない……
もう声が聞こえてもいいはずだ。
自転車以下のスピードに減速している。
女に声をかけようと、バイクから降りようとする。
しかし、妙なことに彼女は強く腰に回した手を放さない。
先輩の腹部に、固く、本当に固く結ばれた彼女の手が見えた。
「おい、止まったぞ。大丈夫や、はよ、はなせよ」
確かめるように、彼女に言うが、返事がない……
もしかして、ヘルメットしているから聞こえないのかな、と自分のヘルメットをとってみた。
さらに、キーを回し、エンジンを切る。
まるで、ヘッドフォンステレオを急にはずした時のように、夏の虫の声が先輩の耳にはいってきた。
夢から、現実の世界に帰ってきたような気分を感じていた。
なんとか、首をまわして、後ろをふりかえるが、彼女は見えない。
固く自分の体に結ばれた手だけが、とても不気味だ。
すると急に虫たちの声が、嘘のように止んだ。
シーンと静まりかえった道の脇で、先輩はバイクの上に立ち往生している。
ライトで照らし出された先には、小さい小川が流れているのが見えた。
ここからだと、その小川のあたりは下りだ。
小川の上には、歩道用の小橋がかかっている。
そうだ。この上が展望台なのだ。
そのとき、ガサガサガサと草をかき分けて、何かが上の山の傾斜の上からゴロゴロと転がってくる音が聞こえてきた。
それは一直線に先輩のバイクに向かってくる!!
そして、バンっ!!と先輩のバイクのマフラーにぶち当たった。
その物体はそのままバイクの少し前方へ転がっていった。
恐る恐るマフラーを確認してみると、何か赤黒いものがベットリ付着している。
これは……血だ!
黒い土と、粘っこい血液がベットリと、鈍く光る銀色のマフラーにこびりついているのだ!!
今まで走っていたバイクの熱いマフラーはみるみるうちにその血を焼き、煙をあげる。
その匂いに先輩は吐き気を覚え、顔をそむけた。
そして、思い出したかのように、いま転がっていったものをバイクのライトで追うと、それは、浅い小川の中を転がりながら、小橋の壁にぶつかって止まった。
ライトが、その後を追う。
はじめは目を疑ったが、それは人間の頭部のようだった……
それも見覚えのある顔。いままで自分の後ろに乗っていた美しい女の顔!!
「はっ、はううっ!!」
声にならない!!
そしてそのとき初めて、彼女が強く先輩の腰に回していた手が、崩れるように、解き放たれた。
どさっ!!とバイク後部に崩れ落ちる彼女の首無しの体……
そして次の瞬間の出来事に、先輩は気を失いそうになった。
彼女の首が突然目をキョロキョロさせ、「私、どおしたん?」と……
その事故の後、先輩は精神不安定と医者に診断され、病院へ入院することになった。
僕がこの話を聞いたのは、先輩をお見舞いに病院に行ったときだが、そのときの先輩のギラギラした眼が今も忘れられない。
されにこの話には後日談がある。
しばらくして正気を取り戻したかに見えた先輩は退院したが、結局、彼女を失ったショックからか、事故のあったカーブの近くの谷底に身を投げて死んでしまった。
それからというもの、その近辺で、妙な噂が流れるようになった。
「首のない女を後ろに乗せ、女の首を脇に抱えたグチャグチャの顔の男がカーブを信じられないスピードで曲がって行き、その先でフッと消えてしまう」
というのだ。
先輩のことは友人や親族以外、誰も知らない。知っていても、事故で亡くなったぐらいしか、わからないのだ。
先輩の葬式が終わって、一週間とたたない内にこの気味の悪い噂は流れ出した。
ある車の運転手はこう言う。
「カーブの先の道の真ん中に丸いボールが転がってたんで、急停車したら、急にそのボールがきえた。不思議に思って、車を降りてみると、自分の後ろの坂道から首が転がってきた」
そして、走り屋の一人はこう言う。
「降りて、そのボールを道の脇によけようとすると、それは実は女の首で、驚いて腰をぬかしてると、いつのまにか音のしないバイカーがとなりにいて、その首を拾ってゆく」
私は確信している。まだ、あの先輩は彼女と一緒に六甲山ハイウェイにいる。
あの展望台にたどりつくまで、カーブを何回もクリアして。
[出典:大幽霊屋敷~浜村淳の実話怪談~]