塚原俊夫君が、魚釣りを好むことは、これまでまだ一度も皆さんに紹介しませんでしたが、俊夫君は、かつて動物学を修めたとき、ことに魚類の解剖と生理とに興味を持ちまして、それと同時に魚釣りも大好きになったのであります。
近頃では、むずかしい事件を依頼されると、わざわざ魚釣りに出かけて考えをまとめることもありましたが、多くの場合は、半日か一日を面白く遊んで頭脳を休めるために、魚釣りに出かけるのでした。
魚釣りの場所は、言うまでもなく東京の郊外ですが、これという決まった所へは行きませんでした。時としては二里も三里も離れたところへ行くことがありまして、いつの場合にも私がそのお供を仰せつかったことは申すまでもありません。私も小さい時分から魚釣りが好きですから、いつも喜んでお供をしました。
ある日、私たちは、久しぶりに、東京府下××村の方面へ鮒釣りに出かけました。それは柿の実がようやく色づきかけた十月なかばの、小春日和ともいうべき暖かい日でして、私たちは午後の陽光を浴びながら、釣り竿を担いで色々の話に笑い興じ、元気のよい歩調で野道を歩いてゆきました。
すると先方から一人の巡査が佩剣を光らせ、今一人洋服を着た紳士と連れ立ってこちらへ歩いてきましたが、洋服の紳士は私たちを見るなり、にこりと笑って、
「やあ、俊夫君じゃないか?」
と言いました。見るとそれは「Pのおじさん」すなわち警視庁の小田刑事です。
「こりゃ、よい所で逢った」
と小田さんは立ちどまって言葉を続けました。
「実は、今日これから君のところを訪ねようと思ったんだ」
こう言ってそばの巡査を顧みて、何やら小声で相談し、さらに俊夫君に向かって言いました。
「実はこの村に殺人事件が起こって、有力な犯人と目星をつけていた男を逮捕してみると、それがどうやら犯人ではなさそうなので、みんなが困ってしまったんだ。君一つ、働いてくれないか?」
俊夫君は魚釣りに来たことなど、すっかり忘れてしまったと見え、言下に「よろしい」と返事をしましたので、小田さんたちは道を引っ返し、私たちを案内してやがて四人は村の駐在所へ参りました。小田さんと連れ立っていた駐在所詰めの巡査は俊夫君に向かって、次のごとき事件の顛末を語りました。
この村には山田留吉という生まれながらの白痴があるのだそうです。留吉は今年十五歳ですけれども、その知恵は三歳の小児にも劣っております。しかし神様は、彼に知恵を与えることを惜しみたもうた代わりに、彼の五官器のうちのあるものを、普通の人間よりも遥かに鋭敏ならしめたもうたのであります。
すなわち留吉の眼は猫よりも鋭く、またその鼻は犬よりも敏いのであります。そのうえ彼は筋力にもすこぶる恵まれておりまして、一口にいえば、猩猩のように強かったのであります。彼は人間の話す言葉を解することができぬと同時に、人間の使う言葉を話すことができませんでした。したがって彼は、顔や形こそ人間ですけれど、その性質はむしろ動物に近いといった方が早わかりであります。
村の人はそれゆえ、彼を指して「人間の猫」だといいました。東京に近い地方でありながら、村の人たちはかなりに迷信深く、彼の生まれたのは、彼の祖父が猫を殺した祟りだと解釈しました。実際、彼は鼠こそ捕りませんでしたが、魚の姿を見ると、その魚が誰の手にあっても、すぐ飛びかかっていって奪い取り、生のまま、むしゃむしゃ食べるのでした。
たまたま、彼の家の前を、魚を携えて通る者があると、それを嗅ぎつけて、家の中から走りだし、あっという間に盗ってゆくので、村の人々は、魚釣りの帰りなどにはけっして彼の家の付近を通りませんでした。なおまた、彼は二三日魚を食べないと、たとい雪の降る日といえども、川の中へ飛び込んで、巧みに魚を捕らえてきては貪り食べました。
魚を携えて近寄らぬかぎり、留吉はけっして村人に害を加えませんでしたし、また、別に性の悪いいたずらもしませんでしたから、村人はどちらかというと、彼の薄運に同情しておりますが、さりとて誰一人彼を可愛がるものはありません。
しかしながら彼は、村人に可愛がられない代わりにその母親によってこの上もなく可愛がられました。彼の父は彼の七歳のとき病死しましたので、母親は一人っ子の留吉を杖とも柱とも思いましたが、留吉は母親の強烈な慈愛をも、まるで感じないかのように暮らしました。
「わたしが死んだら、留吉はどうなるだろう。けっして私は留吉より先へ死んではならぬ」というのが、ことし四十五歳になる母親お豊の平素の願望でありました。家には相当の財産もあって、女中や作男は置きませんでしたが、村の人に田を作らせて取る年貢米は、母子二人の生活を支えるに十分でありましたから、瓦葺きのこじんまりした家に、二人は比較的平和な日を送っていたのでありました。
ところが、母親お豊の平素の願望は、今より二週間ほど前、彼女の非業の死によって微塵に砕かれました。すなわち、ある夜、彼女の家に何者かがしのび入って、彼女を、絞殺し去ったからであります。
最初、変事を発見したのは、市さんという村の遊び人でした。市さんは長らく東京にいましたが、最近郷里に帰ってぶらぶら遊んでいるのでした。東京で何をしていたのか誰も知りませんが、自分ではある呉服屋の番頭をつとめていたところ、最近少し呼吸器を害したから、静養かたがた帰っているのだと申しているそうです。しかし、一見したところでは呼吸器の悪そうな顔もしていないそうで、天気さえよければ、朝早くから魚釣りに出かけることにしていたのです。
その朝、例のごとく市さんが、釣り竿をかついで、留吉の家のそばを通りますと、いつもその時間には開いているはずの雨戸が、その日に限ってしまっておりましたので、不審に思って、裏の方へまわって見ますと、裏口の戸があいていたので、暗い中をのぞきこむように頭を差し入れますと、魚籠のにおいを嗅ぎつけたと見えて、留吉が中から走りだしてきました。
留吉は妙な唸り声を出して魚籠の蓋をあけましたが、空であったから、がっかりした様子でした。しかし市さんは、留吉の様子がなんとなく変に思われたので、奥の間へ入ってゆくと、表の雨戸の隙間からくる光線で、母親お豊が蒲団から身体を半分ほど乗りだし、首に手拭いを巻かれて横たわっているのが見えました。手を触ってみると、もはや冷たくなっていたので、アッと驚いて走りだし、とりあえず村の駐在所に急を報じたのです。
直ちに電話で、この駐在所を管轄しているB署に急が報ぜられると、B署から探偵と警察医とが駆けつけました。取り調べの結果、お豊は前夜十一時頃に絞殺されたもので、お豊の寝室にあった箪笥の引き出しが一つ残らず開けたまんまになり、その内容が攪き乱されているところを見ると、殺害の動機は窃盗であると察せられました。
お豊の家は四間から成っていて、お豊は仏壇の置いてある座敷を寝室としていましたが、その隣の納戸には、留吉の寝床が敷かれてありました。首に巻きつけられて絞殺に使用された手拭いの他には、これという犯人の手掛かりはなく、家の周囲を見ても、近ごろいっこう雨が降らぬので、足跡などは発見することができませんでした。また、その後に行われた死体解剖の結果も、絞殺ということを確かめることができたばかりで、何の手掛かりをも与えませんでした。
ところが、幸いにも、たった一つの手掛かりである手拭いが、村人の証言によってこの村の無頼漢で独り者の信次郎の所有であると分かったので、警官たちが時を移さず信次郎の逮捕に向かうと、彼は早くも風を食らって逃げた跡でしたから、いよいよ犯人は信次郎に違いないということになり、諸方へ手分けして捜査したのですが、彼の行方はとんと不明でありました。
すると、お豊殺害の日から十二日を経た一昨日の朝、行方を晦ましていた信次郎が、飄然として帰ってきたのであります。彼は四十前後の人相の悪い男です。巡査は直ちに彼を引っ張っていきましたが、彼は驚いて何事も知らぬと弁解しました。
しかし、手拭いを見せると、たしかに自分のものだが、いつ落としたか知らないと申しましたので、巡査が事情を告げると、彼は凶行の行われた日の夕方、千葉の旧主人の病気を見舞いに行ったが、案外重かったので家人に留められるままに滞在した旨を語りました。
そこで、昨日、警察の手によって、彼の滞在した先を取り調べると、果たして彼の言葉どおりで、凶行の夜には彼がこの村にいなかったことが分かりました。
さあ、そこで事件は迷宮に入ってしまったのです。死骸は焼かれてしまったし、留吉の家には何の証拠があるでなし、なんともはや手のつけようがないので、とうとう警視庁から小田刑事が出張したのですが、小田さんも事情を聞いて、とても自分の手では解決がむずかしいと思われたので、俊夫君に依頼しようとしたところへ、私たち二人が行き会ったというわけなのです。
俊夫君は、巡査の語るあいだ黙って聞いておりましたが、やがて、
「白痴の留吉はどうしましたか?」
と尋ねました。
「お豊さんの従妹に当たる人が、留吉の家へ来て世話をしています」
と、巡査は答えました。
「あなたがたは留吉を尋問しましたか?」
と、さらに俊夫君は尋ねました。巡査は驚いたような顔をして俊夫君を見つめながら、
「人間の言葉が分からぬのに、尋問ができますものか」
と答えました。俊夫君はにやりと笑いました。そうして、
「だからいけませんよ。留吉を尋問しないで、どうしてこの事件が解決つくものですか」と、事もなげに言いました。
小田さんはじめ、私たちは呆気にとられて俊夫君の顔を見つめました。
しばらくして小田さんは、
「それでは君は白痴を尋問するのか?」
と尋ねました。
俊夫君は意地悪そうな笑い方をしました。
「そうでないですよ。白痴の家で行われた犯罪なら白痴が知っているはずだというだけです。それよりもまず絞殺に用いられた手拭いを見せてもらいましょう」
白痴、山田留吉の母お豊の絞殺された手拭いはB署に保管されてありましたので、小田刑事と駐在所巡査とは、俊夫君と私とを案内して半里ほど隔たったB署に連れていってくれました。私は不要になった二人分の釣り道具を担いで歩きながら、俊夫君がこの事件をどんな風に探偵するであろうかと色々考えました。
手拭いの持ち主たる信次郎は、有力なる嫌疑者として逮捕されたけれども、殺害の行われた時には村にいなかったのですから、彼は犯人ではありません。してみると、誰かが彼の手拭いを拾ってお豊を殺し、彼に疑いのかかるように計画したのか、あるいは信次郎の手拭いをお豊が持っていて、ただ犯人がそれを使用したのだったにすぎないかもしれません。
いずれにしても信次郎が犯人でないとなってみると、誰に疑いをかけてよいか分からぬので、警察の人がはたと当惑したのは無理もありません。この上はその手拭いを検査して何かの手掛かりを得るより他はないが、果たして俊夫君が見事に手掛かりを発見することができるだろうか? と私はひそかに胸を躍らせながら、B署の門をくぐりました。
すると、その時、一人の男が、署の中から急ぎ足で出てきました。田舎者らしくない風采をした彼は、俯きがちに私たちのそばを通りすぎようとしましたが、そのとき私たち一行のうちの巡査は、
「市さん、ご苦労だね」
と声をかけました。男は顔を上げましたが、なんとなく落ちつかぬ様子をして何やら口の中で返事をしながら逃げるようにして去りました。
「あれが、お豊さんの殺されたのを最初に発見した市さんです」
と巡査は小田刑事に向かって告げました。小田さんはただ頷いたのみでしたが、俊夫君は立ちどまって男の姿の見えなくなるまで見送っておりました。
やがて私たちはB署の応接室で署長に面会しました。小田さんは署長に俊夫君を紹介し、凶器として使用された手拭いを貸してもらいたいと申し出ました。署長は、よく太った、赤ら顔の気の短そうな人でしたが、快く承諾して、ベルを押し一人の巡査を呼んで言いました。
「君、尋問室の僕の机の右の引き出しに、例の手拭いが入れてあるから持ってきてくれたまえ」
巡査は頷いて出てゆきましたが、しばらくすると帰ってきて、
「署長、引き出しには手拭いがありません」
と告げました。
「なにッ?」
と署長は驚いて出てゆきましたが、それから五分たたぬうちに署内は大騒ぎになりました。
唯一の物的証拠であった手拭いが紛失したのであるから、警察としては大失策と言わねばなりません。
署長の話によると、信次郎が犯人でないと分かったので、さらに先刻、凶行の最初の発見者たる市さんを呼び寄せて尋問し、市さんに説明を求めるために、手拭いを出して色々尋ねたのであるから、今から十五分前までは手拭いがたしかにあったはずだとのことでした。署長は非常に狼狽して、市さんが盗んだかもしれぬと言って、市さんの後を追わしめて、市さんを呼び戻し、身体検査をさえ行いましたが、ついに手拭いは発見されませんでした。
「署長さんはたしかに手拭いを右の引き出しにお入れになりましたよ」
と市さんは身体検査が済んでから申しました。
市さんを帰してからなお署長は念のために、机の引き出しやその他のところを捜しましたが、手拭いはとうとう見つかりませんでした。してみると、警察署の内部の人が盗んだのか、あるいは外から盗賊が入って盗んでいったのかもしれません。しかし、果たして手拭いが盗まれたとすると、盗人は何の目的でそんなことをしたのでしょうか。警察の人を困らせるための単なるいたずらでしょうか。あるいはもっと重大な理由があるのでしょうか。
いずれにしても署長は、手拭いを失って非常に恐縮し落胆しました。俊夫君はその姿を見て同情したと見え、
「署長さん、手拭いのなくなったことを心配してはいけませんよ。手拭いが盗まれたのでかえって事件の手掛かりができましたよ」
と申しました。
署長はびっくりして俊夫君を見つめ、
「ど、どうしてですか?」
と尋ねました。
「手拭いを盗む者は犯人より他にないじゃありませんか。だから、犯人は、高飛びしないでこの付近のどこかにいるということが分かります」
「でも、その犯人が誰だか分からぬじゃないですか?」
「そうですよ。だからこれから犯人が誰だかを探偵しようというのです。信次郎はまだ拘留してあるでしょう? ちょっと会わせてくれませんか?」
犯人嫌疑者の信次郎は、無頼漢と評判されているだけに、あまり人相のよい男ではありませんでした。俊夫君は信次郎が連れられてくるなり、じっと彼の顔を見つめておりましたが、しばらくしておもむろに尋ねかけました。
「信次郎さん、お前さんはこれまで度々お豊さんの家へ行ったことがあるかね?」
「畑の耕作を頼まれて、時々出入りしました」
「あの手拭いはお豊さんの家へ忘れてきたのではないかね?」
「いいえ、ちがいます。もう長いこと伺いませんし、たしか先月のお祭りのときまでは、あの手拭いを持っていたと覚えています」
「ふむ、そうしてお祭りからこちらへは、お豊さんの家へは行かなかったのだね?」
信次郎は頷きました。
「お祭りの時には、村の人たちと集まって酒でも飲んだかね?」
「ええ、すっかり酔ってしまいましたよ」
「その時は村中の人が集まっていたかね?」
「いいえ、祭りの組は五つに別れているのです。私たちの組は二十軒ばかりです」
「すると二十人ばかりの人が集まったのだね? 集まった人は誰々だか分かっているかね?」
「分かっております」
「お豊さんの家は、その組へ入っているかね?」
「入っておりません」
「何という人の家が祭りの宿だったね」
「市さんのところでした」
俊夫君はしばらく腕を組んで考えました。
「市さんはお豊さんの家へは折々訪ねてゆく様子だったかね?」
「さあ、それはよく存じません」
「もうよろしい。よく聞かせてくれました」
信次郎が去ると、俊夫君は署長に向かって言いました。
「署長さん、もう信次郎は放免してもよいではありませんか?」
「むろん今日は帰すつもりです。で、犯人の見込みはつきましたか?」
と署長はこの小さい探偵の姿を好奇心をもって見つめながら言いました。
「まだ分かりませんよ。まず、お祭りの時に信次郎といっしょに集まって酒をのんだ連中を調べねばなりません」
「しかし、何の証拠もないのに、二十人から調べたところで何にもならぬじゃありませんか?」
と署長は反問しました。
俊夫君はにこりと笑いました。私たちは俊夫君が何を言いだすかと、固唾をのんで待ちかまえました。すると俊夫君はいつものとおりの快活な口調で語りかけました。
「言うまでもなく、今度の事件では何一つ物的証拠というものはありません。たった一つの証拠はさっき盗まれてしまいました。だからこうした事件には顕微鏡も試験管も何の役にも立ちません。もし手拭いが盗まれずにいたら、僕は手拭いの塵埃を集めて検べるつもりでしたが、今はかえってその面倒もなくなりました。どうせ手拭いを検べたところで、おそらく何の手掛かりもありますまい。
もし手拭いに手掛かりがありそうならば、何をさしおいても、捜しださねばなりませんが、その必要がないから僕は打っちゃっておくのです。しかし手拭いを盗まれたということは、手拭いそのものよりも、はるかに尊い手掛かりを与えてくれました。
前にお話ししたように、それによって犯人がまだこの付近にいるということが分かります。凶行後二週間も過ぎているのに、まだ逃げなかったということは、犯人がけっして自分に疑いはかからぬものと安心していた証拠です。つまり真犯人は信次郎が犯人とされるに違いないと思っていたのです。
ところが犯人は信次郎でないと分かり、再び手拭いが別の意味での証拠物件となったので、犯人はまんまとそれを盗んでゆきました。それゆえ犯人はまたもや安心して、どこへも高飛びはしないと思います。犯人が高飛びしなければ、捕まるに決まっております。科学探偵という仕事は、物的証拠を科学的に検べるばかりが能ではありません。犯人を科学的な方法で捕まえるのも科学探偵中の重要な部分です。だから僕は、今回の事件で、犯人の科学的逮捕を試みようと思うのです」
私たちは、みな俊夫君の言うことをよく理解することができませんでした。
「科学的逮捕とはどんなことをするものかね?」
と小田刑事は尋ねました。
「手拭いを盗んだのは、この署内の人かまたは信次郎とお祭りの時にいっしょに酒を飲んだ連中のうちにあるに違いありませんから、それらの人を集めて、科学的に犯人を選びだすのです」
「どうやって選びだすのかね?」
俊夫君はずるそうな笑い方をして、大声で言いました。
「白痴、留吉の知恵を利用するのですよ……」
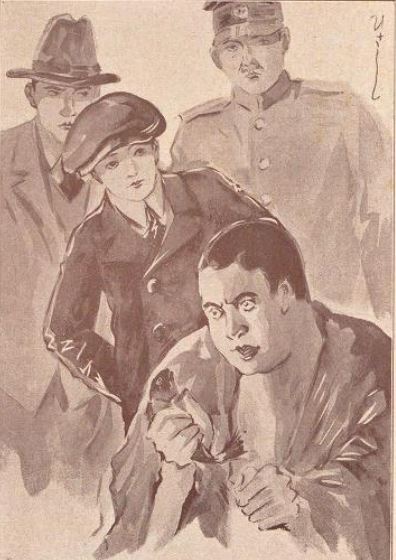
私たちは、あまりの意外に、黙って俊夫君の顔を見つめるだけでした。
「だって俊夫君、留吉は物を言うことさえできぬじゃないか? 年齢は十五だそうだが、その知恵は三ツ児にも劣っているそうだよ」
とようやく小田さんが口をききました。
「けれどPのおじさん、白痴でも人間の子ですよ、犬や猫とは違います。とにかく、これから留吉に会おうと思います。案内してください」
と、俊夫君は申しました。
再び、小田さんと、駐在所の巡査に案内されて、私たちは留吉の村に引き返しました。俊夫君は途中の魚屋で三寸ほどの鮒を一匹買い、それに新聞紙を幾重にも巻き、外から少しもにおいのせぬまで包んで、ポケットに入れました。
留吉の家についた時は秋の日が暮れかかっておりました。四十ばかりの女の人が私たちを出迎えましたが、それは死んだお豊さんの従妹に当たるお安さんという人でした。留吉はその時、どこかへ遊びに行って留守だったので、俊夫君は、まず凶行のあった室を始め、家じゅうをざっと検査しました。と、その時、留吉がひょっこり帰ってきました。
白痴に特有な青白い無表情な顔でしたが、年のわりにはいくぶん老けて見えました。彼は私たちの姿を見るなり、怪訝そうな目つきでぼんやり立っていましたが、やがて何思ったか、畳の上へあがってきました。これを見た俊夫君は、ポケットの包みを取りだし、それを右手につかんで、だんだん彼の方へ近寄ってゆきました。
すると、俊夫君と留吉との距離がおよそ二間ほどになった時、留吉は急に鼻を蠢かしかけたが、いきなり猛烈な勢いで俊夫君に躍りかかったかと思うと、アッという間に新聞包みを奪って逃げてゆきました。俊夫君は黙って笑うだけでした。
「Pのおじさん、これで留吉の尋問はすみましたよ」
と俊夫君は申しました。
「え? けれど留吉は逃げてしまったじゃないか?」
と小田さんは呆気にとられて言いました。
「逃げていってもかまいません。今の尋問で留吉の知恵はじゅうぶん分かりましたから、この上は彼の知恵を借りて犯人を捜しだすばかりです」
「どうして捜しだすのかね?」
「それでは、ここで、その手順を申しましょう」
こう言って俊夫君は駐在所巡査の方を向いて言った。
「あさっての晩、この家で、東京の俳優にお芝居をさせようと思います。そうしてこの間のお祭に信次郎といっしょに、市さんの家で酒をのんだ二十人ほどの村の人に、見物に来てもらおうと思います。で、どうかご苦労ですが、皆さんに十時頃にこの家へ集まってもらうよう言い伝えてくださいませんか。それから」
と、お安さんを呼びよせ、
「留吉にはあさっての夜まで、一匹も魚を食べさせないようにしてください。きっとですよ」
俊夫君はさらに、小田さんに向かい、
「どうも色々ご苦労様でした。これから東京へ帰りがてら、明後日の夜の手順を、相談いたしましょう」
俊夫君が道々話したところによると、芝居といっても、普通劇場で行われているようなものではなく、二人の役者に、お豊さん殺しを演じさせるというのでした。すなわち、一人をお豊さんに扮装させ、今一人を曲者に扮装させて、なるべく、お豊さんの殺された時の光景に近い状態を実演させようというのでした。
俊夫君の説によると、人間の死ぬ刹那には、人間の霊魂は第一に愛するもののところへゆくから、白痴はきっと母親の殺されたときに眼をさましたに違いなく、したがって、おそらく犯人の顔は見たに違いない。けれど残念なことに彼はそれを口に出すことができないのである。そこで今、彼の前で当夜の光景を再演したならば、きっと犯人を思い出し、二十人のうちの誰かに飛びかかっていくに違いない。そうすれば、その飛びつかれた男が犯人であるというのでした。
小田さんも私も、これを聞いて平素の俊夫君に似合わぬことを言うなと思いました。何となれば、俊夫君はこれまで霊魂の存在を信じていないからでありまして、科学的に自分で実証し得ないものはけっして信じないというのが俊夫君の口癖です。だから俊夫君がかようなことを言うには、何かその理由があるに違いありません。で、小田さんは俊夫君の言うままに二人の適当な俳優を雇ってくれました。
翌日、二人の俳優が私たちの実験室を訪ねてきました。俊夫君は、留吉の家の絵図を書いて芝居の行われる場所を説明し、扮装その他、実演事項について詳しい注意を与えました。
いよいよ当日がきました。私たちは小田刑事と二人の俳優とともに夕方から、留吉の村に自動車で駆けつけました。俊夫君は小さな手鞄の中へ、紙で厳重に包んだものを入れて携えました。
最初、駐在所を訪ね、それから巡査とともに留吉の家に行きました。それは八時頃でした。お安さんは快く出迎えてくれました。留吉は二日間魚を食べなかったためか、元気がなく、奥の間に寝ころんでおりました。おいおい村の人が集まってきました。弥次馬も来たようですけれど、巡査のために追いかえされてしまいました。
十時頃、予定の人数はみな揃いました。みんな面白い狂言でも見せてもらえることと思っているようでした。ことに、かのお豊さんの死体を最初に発見した市さんは、一杯機嫌でやってきて、東京通のこととて、色々東京の芝居の話などをみんなに聞かせておりました。
俊夫君は、村の人を、土間と座敷との中間に位する室に、半円形に一列にならべ座らせました。それから、座敷すなわち凶行の演ぜられた室に、寝床を敷いてもらいました。人々はいずれも意外な面持ちを致しました。寝ころんでいた白痴留吉は、沢山の人の集まったのに多少興奮したのか、その辺を歩き回っていました。
十時半になったとき、俊夫君は村の人に向かって言いました。
「皆さん、よく集まってくださいました。今夜集まっていただいたのは他ではありません。皆さんにお豊さん殺しの犯人を逮捕する手伝いをしていただきたいと思ったからです。ちょうど今はお豊さんが殺された時刻ですから、これからお豊さん殺しの芝居をやって、留吉に見せようと思うのです。
そうすれば、お豊さんの一念が留吉にこもっているのですから、留吉はきっと犯人を見つけだすだろうと思います。よもや皆さんの中に犯人があろうとは思われませんが、とにかく一度ためしてみますから、どうかお静かにご覧を願います」
あたりは水を打ったように、しーんと静まり返りました。やがて留吉はお安さんとともに、俊夫君の指図によって、座敷の手前の右隅に座りました。それから、俊夫君はお豊さんに扮装した俳優を蒲団の中へ寝かせました。薄暗い電灯の光に照らされた寝姿は、お豊さんが生き返ったのではないかと村人に思わせたと見え、村人はいずれも固唾を呑んで見つめました。俊夫君と私とは村人の列の後ろに陣取り、小田さんと巡査とは土間に降りたって警戒しました。障子その他の建具はむろん取りはずしてあります。
間もなく柱時計が寂しい音をたてて十一時を報じました。と、その時、納戸の方から黒い布で覆面した一人の曲者が、一本の古手拭いを手にさげて、みしりみしりと歩いてきました。彼は閾のところでしばらく立ち止まって考えていましたが、やがて膝を折って、お豊の枕元の方へ近よりました。さすがの留吉も、じっとその方を見つめておりました。村人は、一生懸命に、いわば我を忘れてこの真に迫った演劇を眺め入りました。
枕元まで近寄った曲者は、蒲団に手をかけたかと思うと、ぱっとそれをはねのけました。とその時、お豊さんは「アレー」と一声、逃げだそうとしましたが、曲者はとびかかって手拭いで手早く首を絞めましたので、お豊さんは、蒲団の外へ半身をのりだし、どたりと倒れました。
その時です、白痴留吉は何思ったかくるりと村人の方を向きましたが、次の瞬間ぱっと立ちあがったかと思うと、ちょうど俊夫君の前に座っていた市さんの首筋めがけて飛びかかったので、市さんはアッといって仰向けに倒れましたが、留吉は死に物狂いで、何物をか捜そうとするかのように、その身体に乗ったり降りたりしてあばれました。
「アア、いけないいけない。留吉、堪忍してくれ、お前のお母さんを殺したのは俺だッ!」
と、市さんは苦しそうに叫びました。
皆さん、お豊さんを殺したのは市さんでした。市さんはその場から警察へ連れられてゆきましたが、村の人はあまりのことにびっくりしてろくに口をきく人さえありませんでした。
市さんの白状するところによると、金に困ってかねてからお豊さんをねらい、祭の時に信次郎の手拭いを拾ったので、お豊さんを殺して金を奪い、手拭いをそのままにしておいて信次郎に疑いのかかるようにたくんだとのことでした。その夜、帰京の途上、俊夫君は小田さんに向かい次のように語りました。
「凶行を発見したのが市さん、信次郎といっしょに酒を呑んだのが市さん、それから警察で手拭いを盗んだのが間違いなく市さん。で、僕は犯人が市さんだろうと見込みをつけ、一芝居やったのです。市さんが一生懸命に芝居を見ているうしろで、僕はお豊さんが首を絞められる時に、鞄の中の鮒の包みをとりだしてひょいと市さんの肩のそばへ差しだしたのです。
留吉は二三日魚に飢えていたので、すぐにかぎつけてそれを取りにきたのですが、僕が再び鞄の中へ入れたから、市さんが持っていることだと思って、留吉は大いに捜しました。
しかし市さん自身は、留吉が犯人を思い出したと思い、とうとう白状したのです。科学探偵とは、顕微鏡や試験管を使うことばかりを意味するのではありません。物事を科学的に巧みに応用して探偵することも科学探偵なのです」
