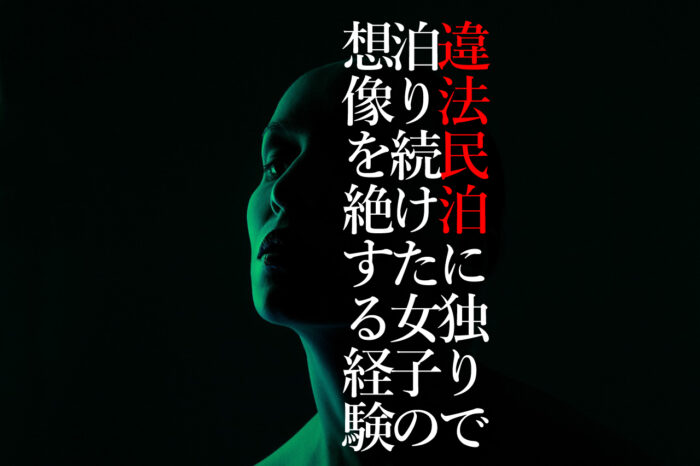私は、仕事の都合で半年ほど、全国を転々としていた。
不動産業界の業界紙の取材で、東京、大阪、名古屋、京都、地方都市を次々に回る生活だった。宿泊費を抑えるため、当時はまだグレーゾーンだった民泊を使った。違法かどうかを深く考えたことはない。ホテルより安く、空いていて、予約が簡単だった。それだけだ。
結果として、七月から十二月までに、六十泊以上、民泊に泊まった。
今思えば、それが「泊まった」という表現でよいのかすら、分からない。
最初の違和感は、秋口の東京だった。大田区の古いマンション。チェックインして部屋に入った瞬間、私は無意識に室内を確認していた。風呂場、押し入れ、クローゼット、ベッドの下。誰かが潜んでいないかを探すような動きだった。
自分でもおかしいと思った。だが、民泊では鍵の管理が杜撰なことが多い。郵便受けに鍵が放り込まれていたり、キーボックスの暗証番号が初期設定のままだったり、ドアに鍵が刺さったままだったこともある。
誰でも入れる。
そういう場所に、自分は一人で泊まっている。
その前提が、夜になると妙に重くのしかかってきた。
京都の駅前で泊まった物件では、それが決定的になった。深夜十一時過ぎのチェックイン。外廊下の突き当たりの部屋だった。廊下を歩いている途中、隣室のドアが少しだけ開いているのが見えた。暗がりの中、目だけがこちらを見ていた。
私は立ち止まれなかった。視線を外せず、鍵を開け、部屋に入り、内側からロックをかけた。
室内は真っ暗で、照明がつかなかった。ブレーカーが落ちていた。スマホのライトで部屋を照らした瞬間、理由もなく「来てしまった」と思った。誰かが笑った気がしたのは、その直後だ。
布団をめくると、白いシーツの上に黒髪が一本落ちていた。妙に艶があり、乾いていないように見えた。誰かが直前まで使っていた痕だった。
その夜、私はほとんど眠れなかった。
朝、全身に蕁麻疹が出ていた。医者はダニだと言った。私は何も否定しなかった。ただ、納得もしなかった。
それから、似たことが続いた。大阪、江東区、名古屋。どの部屋にも「使われた気配」が残っていた。曇らないはずの鏡に手形が浮かび、冷蔵庫に開封済みの飲み物が入っている。管理がずさんなだけだと、自分に言い聞かせた。
ある夜、テレビもない部屋で寝ただけなのに、朝になるとスマホに動画が残っていた。自撮りカメラで、私の寝顔が七時間分、録画されていた。固定された画角。動かない視線。ホストに連絡しても返事はなく、数日後、その物件はサイトから消えていた。
その頃から、部屋に入った瞬間に分かるようになった。
ここは「空いていない」と。
布団の下、シンクの奥、クローゼットの隙間。誰かがそこにいるというより、そこに「いた」場所に自分が戻ってきている感覚だった。
名古屋で泊まった物件で、私はそれを正面から見た。深夜二時、風呂場のドアが音を立てて開いた。曇った鏡の向こうに、逆さまの顔が映っていた。長い髪と、黒い目。こちらを見て、笑っていた。
逃げようとした瞬間、耳元で声がした。
「今夜も、泊まりに来てくれてありがとう」
その言い方が、どうしても引っかかった。
泊まりに来たのは、私のほうなのに。
外に飛び出して振り返ると、部屋の奥、ベッドの下から髪だけが覗いていた。誰かが潜んでいるというより、私が出ていくのを見送っているように見えた。
それ以来、民泊は使っていない。使えない。
だが、夜になると、枕元に気配がある。耳元で、あの声が聞こえる。
「また、戻ってきてくれるよね」
気づいたとき、スマホの検索履歴に、見覚えのない民泊の物件ページが開かれていた。
予約ボタンが、押される直前で止まっている。
私はまだ、呼ばれている。
[出典:https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171219-00053828-gendaibiz-bus_all&p=1 ]