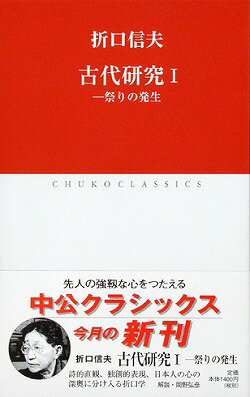初夜権とは

[フランス出身の画家ジュール・アルセーヌ・ガルニエ(Jules Arsène Garnier、1847年 - 1889年)が1872年に発表した絵画「初夜権(Le Droit du Seigneur)」。中央に領主と新婦(妻)、左側に新郎(夫)と説得する神父、周辺に警護する家臣やそれらを見物する民衆が描かれている。ガルニエが初夜権の様子を想像して描いた絵画である]
初夜権(しょやけん)
庶民・領民の結婚に際し、酋長・領主・祭司・僧侶などが花婿に先だって花嫁と同衾する権利
[出典:広辞苑]
メル・ギブソン主演・監督「ブレイブハート」という映画がある。
物語は、西暦1200年代頃の中世の英国での出来事、当時イギリスの植民地だったスコットランドの平民ウィリアム・ウォレスがイギリスの植民地支配に反旗を翻し、英雄的な活躍をするというもの。
しかし、最後には友の罠に落ちて、処刑(八つ裂きに)されるまでを描いた歴史スペクタクル映画。
実はこの映画、『初夜権』という問題がことの発端である。
メル・ギブソン扮するウォレスが愛する女性と『領主の初夜権を忌避するために』密やかに結婚した。
ところが、それが領主の知るところとなり、ウォレスの最愛の妻は領主に浚われ惨殺されてしまう。
ウォレスの反抗(Brave Heart)はここからはじまるのだ。
時(あるいは土地)の権力者が花婿に先だって花嫁と同衾する権利……即ち、この初夜権を持つことが、時の権力者のステータスを意味していた。
『フィガロの結婚』のテーマは初夜権封じ!
それと、モーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」の舞台でフィガロの機知で、アルマヴィーラ伯爵の持つ封建的な『領主権』を封じるという話がある。
この『領主権』というのが、実はフィガロと結婚しようとする花嫁スザンナの『初夜権』のことというのは案外知られていない。
随分乱暴な話なのだが、この『領主権』は、花嫁のお尻の大きさだけのバターを代わりに納めれば免除されたという。
フィガロの結婚・あらすじ
●主な登場人物
・フィガロ(主人公。伯爵の下僕)
・スザンナ(フィガロの婚約者。待女)
・アルマヴィーヴァ伯爵(スペイン貴族)
・伯爵婦人
・ケルビーノ(小姓)
・マルチェリーナ(実はフィガロの実母)
・バルトロ(医師)
●第一幕
城の一室、伯爵の従者フィガロと伯爵夫人の侍女スザンナは、夕方に結婚式を挙げる事になっている。
二人は、その準備をしているが、スザンナが新居と伯爵の部屋が近過ぎることに気がつく。
これは、伯爵が『初夜権』を復活させてスザンナをものにしようと企んでいるからである。フィガロはそれを阻止する決意を表わす歌を唄う。
しかし、フィガロはマルチェリーナから借金をしていて、それが返済できないときはマルチェリーナと結婚するという証文を交していた。
マルチェリーナは、医師バルトロと謀り、フィガロに迫る。一方、スザンナのもとに小姓ケルビーノがあらわれ庭師の娘バルバリーナとの逢引がみつかり、伯爵に追放されそうになっていると、取りなしを頼みに来る。
ケルビーノは、スザンナにも言い寄ろうとするが、そこに、スザンナを口説こうと、伯爵が入ってきたのでケルビーノは長椅子の後ろに隠れる。
すると、音楽教師バジリオがやってきたので、伯爵まで長椅子の後ろに隠れることになる。
スザンナが、なんとか隠そうとするが、結局ケルビーノは伯爵に見つかってしまい、バジリオの告げ口によってケルビーノが夫人に好意を持っていることを知った伯爵は、ケルビーノに軍隊行きを命ずる。
そこへフィガロが村人と共にやってきて、初夜権を廃止した伯爵を賛える。また、ケルビーノをからかう有名なアリアを唄う。
日本にみられる初夜権的俗習
日本における初夜権の存在は、古代の神事や祭祀を起源としたり、地方の風習に痕跡や類似が散見できると推測できるものの、存在の有無まで断言している文献はない。
ただし、世界各国のあらゆる宗教や風習と同様に、成人(大人)になる若者を年長者が祝福し、それを村や町などの共同体の人々に紹介するような通過儀礼はごく日常的に存在していた。
また、処女の女性、あるいは成人に達していない未婚の女性の所有権が神にあるとする考え方が存在していたため、結婚した最初の数日間は神に敬意を表する意味合いで性交を禁じる風習や、新婚夫婦に厄災が降りかからぬように第三者の男性が新婦や処女との性交を代行した事例は散見されている。
したがって、これらの風習や儀式を拡大解釈するという前提であれば、初夜権またはそれと同等の性行為が過去の日本に存在したのではないかと推測できる。
また、神事や祭祀であることから、あくまでも形骸化した儀式や儀礼(セレモニー)へ変化し、近代になるにつれ実際に処女を奪うような性行為そのものは衰退していったのではないかと、推測する。
古代の神道において、神と交流できるのは、男性であれば神主、女性であれば巫女のみであった。
したがって、まだ精通経験のない男性や童貞の男性、初潮経験のない女性や処女の女性は、神や共同体の所有物であり、彼らを成人の社会へ導けるのは神主や巫女のみとされた。
ここから、処女や新婦の女性を臨時的に巫女と同等に見なし、神の代行役である神主や媒酌人が性交することで神の怒りや厄災を回避したとする説がある。また、こういった考え方を受け継いだ風習が近代前後まで各地に残っていたとする説も多い。
中山太郎の著書「日本婚姻史」では、奈良時代の「日本書紀」(允恭紀)や平安時代の「本朝文粋」(意見十二箇条)などを事例に挙げ、神主や「座長(かみのくら)が処女を要求できた」とする説を紹介しつつ、「一種の呪術として処女膜を破る儀式」などが、現代では一般的に解釈される初夜権と同一視されがちだが「似て非なるものであることを注意されたい」と述べている。
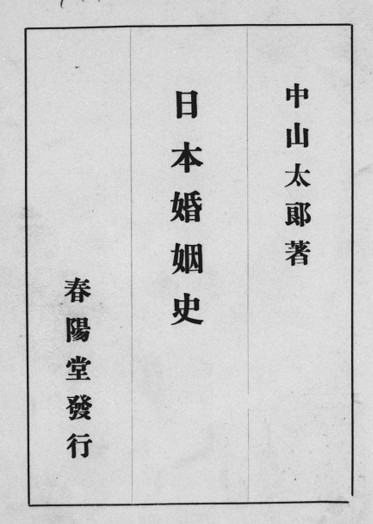
一方で、民俗学者の折口信夫は1926年に雑誌「人生創造」(人生創造社)に発表した「古代研究」の中で、少なくとも奈良時代以前の神主は初夜権と見なしてよい権利を持ち、現人神(あらひとがみ)と見なされた豪族などは「村のすべての処女を見る事の出来た風(確認することが可能だった世情)」が、近代まで残っていたと述べている。
また、朝廷に従える采女(うねめ)や「巫女の資格の第一は神の妻(かみのめ)となり得るか」どうか、つまり処女であるかどうかが重視されており、たとえ常世神(とこよのかみ、神の代理役)であっても現実的に貞操を守り続けることは困難であったため、処女や新婦は一時的に「神の嫁として神に仕へて後、人の妻(ひとのめ)となる事が許される」ような儀式へと変化し、これらが「長老・君主に集中したもの」が初夜権と同等であっただろうと述べている。
また、「神祭りの晩には、無制限に貞操が解放せられまして、娘は勿論、女房でも知らぬ男に会ふ事を黙認してゐる地方」などもあったため、当時の性に対する感覚や処女の立場、初夜権の発生原因などを理解しないと「古事記・日本紀、或は万葉集・風土記なんかをお読みになつても、訣らぬ処や、意義浅く看て過ぎる処が多い」とも述べている。
各地でみられる初夜権らしき風習
栃木県では、結婚式の初夜に「お連れ様(おつれさま)という者を帯同させる」風習があった。
初めての「床のべ(とこのべ、同衾)」の際、「お連れ様は無遠慮にも新夫婦と共に同じ室に枕を並べて寝るのが礼儀」であり、新婚初夜に新郎新婦が性交することはなかった。
これは、栃木県塩谷郡栗山郷の調査で記録されており、「山間の僻村で、昔は他人の顔は一年中にも数えるほどしか見られぬと言われた土地」だったため、「婚姻は概して近親同士」であることが多く、「しかも山では恋を知るのが早く、ことごとく早婚」であったという。
また、「娘十三嫁(ゆ)きたがる(娘も13歳になれば結婚したがる)」という風潮で、「都会であれば通学盛りの小娘が、この地では立派に母親となって」いる土地柄だったという。
前述中山太郎はこの風習を「古くはお連れ様なる者が初夜権を行使したのを、かく合理的に通俗化した」名残りではないかと述べている。
井上ひさしの見解
初夜権という言葉がある。新潮国語辞典によると_
《結婚の際に、領主・酋長・僧侶・祭司などが新郎に先だって新婦と共に寝る権利。未開人の間には今なお残存する》
_そうだが、文献を引っくりかえしてみるとこの慣習は洋の東西を問わず、各地に存在したようである。
たとえば、羽前国(山形県)の米沢市には、婚礼の三日前に仲人が新婦をわが家に泊め、三夜共寝して、式の当日、なぜだかしらぬが餅を百八個添えてその新婦を新郎の家へ届けるというならわしがあった。
紀州(和歌山県)の勝浦港では、自分の娘が十三、四歳になると、老人を雇い、その老人に破素(ナニのことです)してもらうのが通例だったという。
老人はこの仕事の謝礼として米と酒と、これもなぜだか桃色の褌(ふんどし)を受けとるきまりになっていたそうだ。
おぼこ娘と共寝をさせてもらい、そのうえ、謝礼まで貰えるなぞ、羨しいような、嘘のような話だがこれは誓って真実なのだ。
石川県には、娘を嫁に出す前に父親は、村のなかでもっとも数多くの女性と接した男性に頼んで、己が愛娘を試してもらうという風習がかつてあったらしい。
また豊後(大分県)の日田郡夜明村というところには、毎年八月十五日の夜に「ボンボボ」と称する祭りがあったといわれる。
十四歳の娘は、この夜村の長老たちと寝るのである。
このボンボボに参加しない娘は、穴無しと見なされ、一生嫁に行けぬ。それがこの村のきまりなのである。
本邦の例ばかり掲げたが、右の如き事実は外国にもゴマンとある。
ルイ十四世治下のフランスでは、領主が領内の花嫁に「ドロワ・ド・キュサージュ」なる権利を行使することが認められていた。
ドロワ・ド・キュサージュを訳せばつまり「股の権利」である。
ラングーンのペグラというところでは、己が花嫁を友だちのところへやって一夜を過させるというならわしがあったというし、これと同じことはチベットでも行われていた。
マルコポーロの旅行記にもこのことははっきりと書かれている。
また、これはすこし古いはなしだが、バビロニアでは、未婚女性は必ず一度はヴィナスの神殿に詣で、そこの森で他国の男性と交わらねばならないというきまりがあった。
いったいなんだって、初夜権というものがかつて存在したのであるのかしらん、これはわたしの長い疑問だった。
ところがこの疑問がこのあいだあっさりと解けた。
ひょんなことから知り合いになった滞日中のウガンダ人の技師が、雑談のあい間にふとこう言ったのだ。
「むかし、わたしの国では、処女から女になるときに女性の流す血が子孫に危険を及ぼすという信仰がありました。ですから、初夜には、新郎は新婦と寝ないのです。つまり、精液が処女の出血と混ると、生れてくる子どもが早死すると信じられていたわけです」
そういえば紀伊風土記には、高野山の高僧の袈裟に処女の血がかかったとたん、その袈裟が火を吹いて燃えあがった、という伝説も載っている。
つまり、わたしたちの祖先は、処女の血は不吉だ、と考えていたのだ。
そのために、力ある者に処女の血を流し出してもらうという風習、つまり初夜権がかつてあったのではないか。
ついこないだまで(あるいはいまも?)金持は何百万という大金を投じて芸者の水揚げ式なるものを行っていたが、世の中かわれば変るものである。
初夜権の是非はとにかく、若い娘さんたちが処女膜とやらを後生大事に守り、また破られたら貼り替えたりなどして、男どもにすこしても自分を高く買わせようと狂奔しているのをみると、そして、男ともが結婚の相手は処女が一番などとさわぎまわり、相手の娘さんの質の良否よりも膜の有無を気にしているのをみると、わたしはひょっとしたらむかしの人のほうが利口だったのかもしれないな、と思わないでもないのである。
[出典:『巷談辞典』処女崇拝より 井上ひさし(1984年12月25日文藝春秋)]
山梨県南巨摩郡鰍沢町の事例
1959年(昭和34年)の新聞報道。
結婚間近い女性が、仲人役の男から「お礼」を強要されていると甲府警察署に相談。
同署では、仲人役がお礼として婚前に花嫁と関係を結んだ古い因習が残されていた特異な事案として、女性を脅した仲人役への捜査を進めるとともに、法務局人権擁護課にも通告することとしたという。
[出典:山梨時事新聞 昭和34年3月25日]
南方熊楠の見解
あらゆる学問において博識であり、フィールドワーク(現地調査)を盛んに行った博物学者の南方熊楠は、自著の中で何度か初夜権について言及している。
その中で特筆すべきなのは、南方自身が「見たことがある」として述べた著書が存在することである。
これは、1925年に発表した自伝的随筆「履歴書(矢吹義夫宛書簡)」の中の項目「僻地、熊野」で述べられており、文中の書き出しに「紀州の田辺より志摩の鳥羽辺まで」とあることから、故郷の和歌山県から三重県辺りを指す地域と考えられる。
また、「二十四年前に帰朝した」時期とあることから、留学先の欧米諸国から帰国した1900年頃の出来事であったと思われる。
年頃の娘に一升(米)と桃色のフンドシを景物(土産)として神主または老人に割ってもらう所あり。小生みずからも十七、八の女子が、柱に両手を押しつけるごとき威勢でおりしを見、飴を作るにやと思うに、幾度その所を通るも、この姿勢故、何のことかわからず怪しみおると、若き男が籤(くじ)でも引きしにや、「おれが当たった」と、つぶやきながら、そこへ来たり、後よりこれを犯すを見たことあり。
「割ってもらう」とは破瓜を意味し、「おりしを見」とは「折り敷き(おりしき)」と呼ばれる姿勢で「片膝立ちになってみせて」という意味である。
ただし、これを以って南方自身が初夜権であると指摘しているわけではなく、当時の性交経験の年齢が現在よりも格段に低かったことなども考慮すると、くじ引きに当たった男性が犯した「十七、八の女子」が処女だったのかどうなのかは疑問も残る。
実際、この記述の直後に、「十四、五に見える少女」が赤子を背負いながらに若い少年に「種臼(たねうす)切ってくだんせ」と頼む様子も見たことがあると述べている。
「種」は「子種(こだね、男性器)」であり、「臼」を「女陰(にょいん、女性器)」として、仏典の事例から「悟り申した」と推測している。
関連する話
⇒ 田舎の忌まわしい風習で狂ってしまった母ちゃんの話