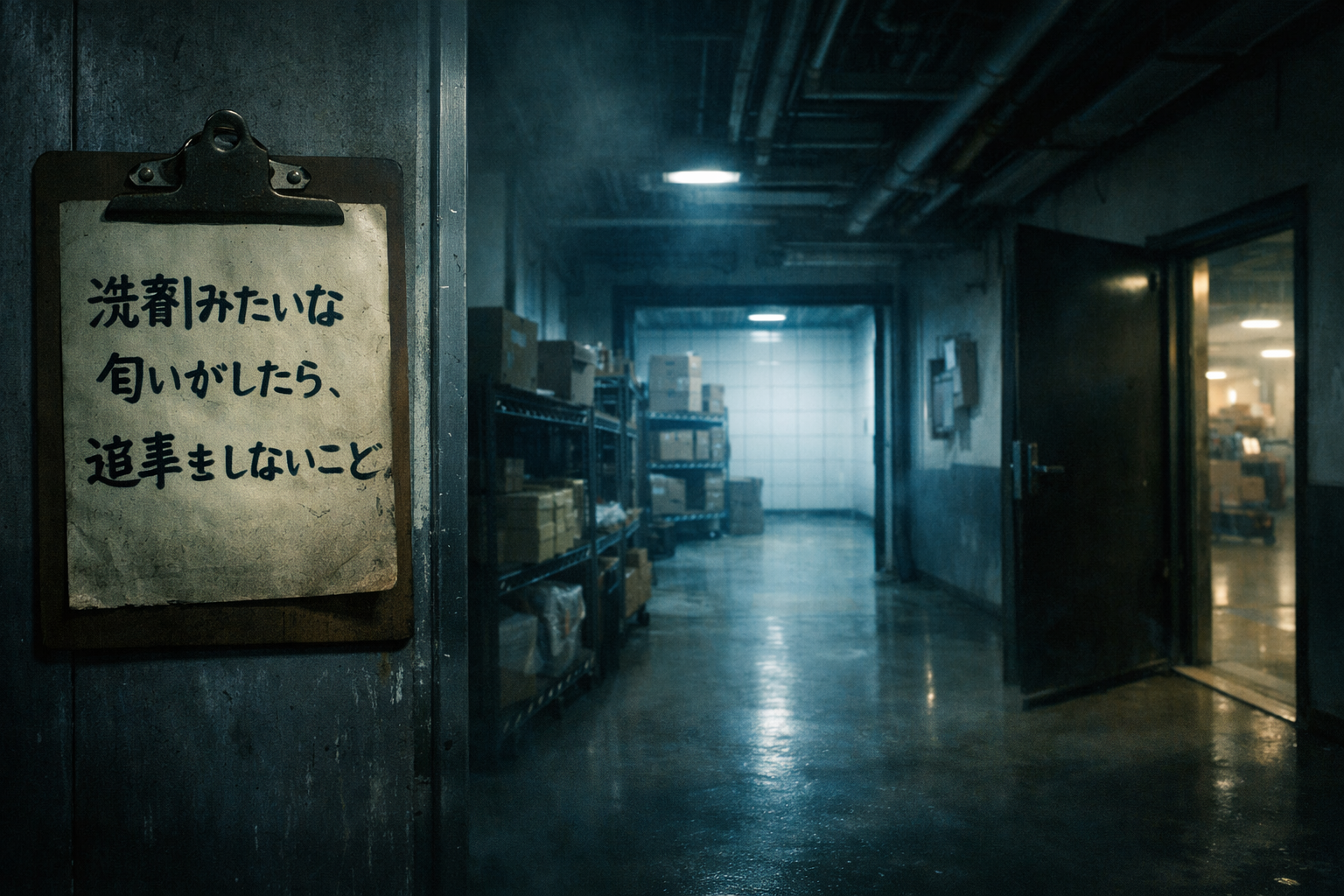知人が体験した話として聞いた。四年ほど前だという。
その知人は、建物の裏側を見るのが好きだった。豪華なエントランスよりも、客が通らない通路の方に興味を持つ。どこがどう繋がっているのか、それを把握していないと落ち着かない性分だったらしい。写真は撮らない。ただ、自分の足で辿る。構造を確かめる。それだけだ。
その日、湾岸の複合ビルに用事があった。イベントで表のフロアは混雑していた。人の流れに押されるのが嫌で、サービス通路に回った。従業員も業者も使っている場所だ。特別なことではない。
通路は灰色で、似た扉が並び、配管が天井を走っていた。曲がり角が多い。床の表示は薄れ、方向感覚が曖昧になる。
彼は何度か「ここを抜ければ近道になる」と判断して進んだ。
気づけば、足音が自分だけになっていた。遠くで換気音が鳴っている。一定の音だが、どこから響いているのかはわからない。
戻ろうとした時、背後の扉が閉まっていた。閉まる音は聞いていない。さっき押して通ったはずの扉だ。取っ手を押しても動かない。鍵の仕様はわからない。警報が鳴るのが嫌で、力はかけなかった。
通路の空気が妙に冷たいことに気づいた。均一に冷えている。どこにも風がないのに、温度だけが揃っている。
それから、匂いがした。
最初は気づかなかった。清掃直後のような、洗剤に似た匂い。だが甘さと、焦げたような苦みが混じっている。鼻の奥に残る種類の匂いだった。
前に進むしかないと判断した。
通路は途中で広がった。壁の素材が変わり、照明の色が青みを帯びる。変化は段階的ではなく、切り替わるようだった。
角を曲がると、倉庫のような空間に出た。ラックが並び、梱包材が積まれている。埃はない。だが人の気配もない。
入り口近くの柱に、クリップボードが吊ってあった。
紙が挟まれている。印刷ではなく、太いペンの手書き。
「洗剤みたいな匂いがしたら、呼ばれても返事をしないこと」
それだけが書いてあった。
彼は、その文を理解する前に、背後で短い音を聞いた。喉を鳴らすような、咳払いに似た音。
呼ばれたとは思っていない。ただ、自分の名前が次に続くと確信したらしい。
振り向かなかった。
返事もしなかった。
その代わり、視界の端に、倉庫の奥の壁が映った。ほかと違う白さだった。塗装か、タイルか、判別はつかない。ただ、継ぎ目の細かさだけが異様だった。
匂いが強くなった。
空気が鼻の奥に貼り付く。
彼は走った。倉庫を横切らず、来た通路へ戻った。角を曲がるたび、背後に同じ足音が増えている気がした。一定の間隔で、追ってくる。
最初に閉まっていた扉の前まで戻った。
取っ手に触れた瞬間、軽く開いた。
抵抗はなかった。
外は、さっきのサービス通路だった。人の声も台車の音もする。
ただ、彼はひとつ思い出せなかった。
最初に通ったとき、その扉は本当に開いていたのか。
閉まっていたから押したのか、開いていたから通ったのか、その順番が曖昧になっていた。
後日、彼は管理会社に問い合わせた。説明した場所に該当する倉庫はないと言われた。白い壁も、途中で戻れなくなる区画も存在しないと。
だが、ひとつだけ返答があった。
その日は、清掃業者の立ち入り予定はなかったという。
それ以来、彼は大型商業施設に入ると、必ず匂いを探すようになった。
見つけたときは、必ず誰かが背後で喉を鳴らす。
呼ばれたことは、一度もない。
ただ、返事をしていないことだけは、毎回はっきり覚えているという。
[志那羽岩子 ◆PL8v3nQx6A]